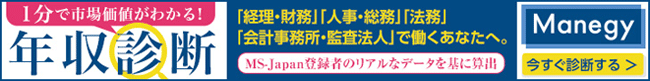女が何気なく本棚にぶつかると、後ろの壁が動き出す。隠し部屋が現れ、そこには大金と札束と金塊が隠されていた―。
映画「マルサの女」で、国税局が脱税疑惑のある経営者の屋敷を調べ上げているワンシーン。女は宮本信子さん演じる主人公の査察官だ。宮本さんの夫で、映画監督として名高い故・伊丹十三さんがこの作品を世に送り出したのは1987年だから今の20代の税理士志望者は、観たことがない人も多いだろう。日本経済がバブルにさしかかる時代の潮流を捉えた社会派のエンターテイメント作品としてヒットした。脚本に書かれた脱税の手口はいかにも「映画的」な見せ場だが、制作に当たっては、当時の国税局の協力もあって取材に基づいたリアリティーを反映している。国税局査察部を意味する「マルサ」という”業界用語”を始めとする税務当局の実態が一般社会に広く知られるきっかけとなった。
警察や検察の”ガサ入れ”を彷彿とさせるシーンだが、これは税務署が行う税務調査の中で「強制調査」と呼ばれる。裁判所の令状に基づいて行われるため、調査対象となった関係者の同意は必要とせず、自宅などを徹底的に調べ上げられる。元国税調査官の大村大次郎氏の著書「脱税」(祥伝社)によれば、億単位が見込まれる大型の脱税事案で主に行われ、時にはドアをぶち破ったり、天井や床下も調べたりすることもあるという。一方、納税者の同意を得て行う税務調査が「任意調査」だ。調査のほとんどはこの方式で行われ、調査日を事前に通告されることも多い。ただ、任意といっても当局には質問検査権があり、納税者は協力が義務付けられている。正当な理由がないのに協力しなければ追徴課税などの罰則を科されてしまう。
実は、税理士の大事な役目の一つがこうした税務調査への対応だ。調査官は帳簿類を徹底的に調べ、後日、様々な指摘事項を通知する。よく追徴課税を受けた企業が報道機関に対し、「当局と見解の相違があった」というコメントを出すが、「見解」とは、どこまでが課税対象となるのか、解釈や事実認定を巡って税務当局や企業側がすり合わせながら、激しい交渉が行われる。その際、税務の素人であるクライアント企業だけでは太刀打ちできず、税理士の出番となるわけだ。税理士の吉澤大氏によると、「現金商売で帳簿残高と実際の残高に誤差はないか」「海外渡航費について消費税が控除対象として処理されていないか」といったことがチェック対象になるという。税法論議だけでなく、当局側が「このくらいは納税して頂かないと上司の許可がおりない」といえば、税理士が「いやいや、そんなに追徴されたら顧問契約を解除されてしまうのでこのあたりで」と落としどころを示す、といった”価格交渉”になることもあるという(出典:吉澤税務会計事務所ホームページ)。
もちろん、帳簿の粉飾や未申告の所得があるなど、決定的な脱税行為は擁護できないが、交渉によって、節税が可能になるケースは多い。クライアントの「盾」として頼りになる税理士を目指したいものだ。