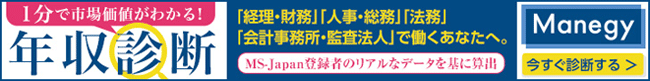華々しく発売された、その新商品の登場を苦々しく見ている人たちがいる―。
新商品とは、米アマゾン・ドット・コム社製の電子書籍端末「キンドル」。母国の電子書籍市場をわずか5年で、紙の書籍の一種ペーパーバック市場を追い抜くまでに急成長させた立役者が、ついに日本に登場した。同社のサイトで夏に「近日発売」を予告してから時間はかかったが、日本の電子書籍市場拡大に弾みをつける存在として期待されている。
キンドルの発売を快く思わないのは誰かと尋ねられたら、多くの人が楽天等の企業を思い浮かべるだろう。インターネット通販でアマゾンと覇権を競ってきた国内最大手は、宿敵が「切り札」を投入するのに先駆け、「Kobo」という端末を7月に発売した。しかし、アマゾンに厳しい視線を送っているのはライバル企業だけではない。
実は、財務省と国税当局が監視の目を光らせているのだ。3年前には、千葉県内にある同社施設が、法人税の課税対象である事業拠点であるとして、当局が140億円を追徴課税。アマゾン側は課税対象に当たらない「倉庫」であると主張して紛糾している。さらに、キンドル登場で、海外から配信されるコンテンツへの消費課税の問題が浮き彫りになっている。海外からダウンロードする音楽や書籍などのデータには現行法では課税できない。一方、国内配信分は課税対象となるため、日本の事業者が不利に立たされている。財務省は、EUを参考に海外からの配信に課税することも検討し始めている(2012年6月25日・日本経済新聞)。
税理士を志望する人にとっても、こうした企業のグローバル化に伴う税制の動きは注目したいところだ。経済のグローバル化が進んだ今日、国境をまたいで複数の事業拠点を抱える企業にとって、進出先の国への納税をどうやり繰りするかは大きな経営課題なのだ。その典型が「移転価格」への対処だ。親会社と海外にある関連会社との取引を行う際の価格のことで、企業は税負担を軽減するため、税率の低い国の会社に利益を集めたいところだ。しかし、そうした企業の思惑を見越し、日本は1986年から、関連企業ではない第三者の企業との取引価格と移転価格が違う場合を考慮して課税する「移転価格税制」を導入しており、税理士は、企業にとっても国にとっても移転価格が適正にするように努めるのが大事な仕事になる。
経済産業省の「外資系企業動向調査(2011年)」によると、日本へ新規参入した進出企業は前年より減少したものの、アジア系企業の割合は増加。約半数の企業が日本で事業拡大をする意向を示したという。外資系企業をクライアントに持つことが今後も増えるだろうし、外資系の税理士法人に就職する機会もあるだろう。語学力に自信がある人はもちろん、日本の内情に詳しくない外資系企業が安心できるようなコンサルティングが出来れば、税理士としてビジネスチャンスは広がるはずだ。