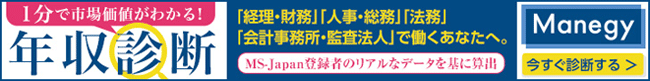プロ野球が開幕して間もなく1カ月が経とうとしている。 WBCで注目度が高まった後のシーズンイン。投手と打者の“二刀流”で話題の日本ハムの大谷翔平選手や、高卒新人としてはドラフト導入後最速の開幕3戦目先発を果たした阪神の藤浪晋太郎投手ら、大型新人の活躍が注目される年になりそうだ。彼らの成長が気がかりなのはファンばかりではない。球団の営業担当者にとっても客足に影響するので切実なのである。
昨シーズンのプロ野球界は終わってみると、営業面で厳しい現実にさらされた。 12球団のうち7球団で観客動員が減少。セ・リーグを制した巨人は6.9%増と全球団で最も高い増加率だったが、パ・リーグ覇者の日本ハムは対照的に6.6%のマイナスだった。近年随一の動員力を誇ってきた阪神も5位低迷の影響で6%近く減少。前年の1試合平均4万人から3,000人ほど客足が遠のいた。前年は東日本大震災や計画停電の影響で春先の試合を急きょ地方で行ったこともあり、観客が減少。各球団の営業担当者は「今年こそは」という思いがあっただけに2年続けての低迷は誤算だった。
12球団のうち、巨人と阪神をのぞく大半の球団が赤字と言われている。毎年、決算が見えてくるシーズンオフになると、親会社が毎年20~30億円を補てんしているという報道がされるのだが、プロ野球が構造的に赤字となりがちな最大の要因が「税金」にあることをご存じだろうか?
その文書が出されたのは、1954年のこと。国税庁長官名義で「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について」という通達が国税局長に出された。通達では、親会社が球団の野球事業で生じた欠損金(赤字)を補てんする際、「広告宣伝費」として損金扱いすることを認めた。まだ日本が終戦の混乱期を抜け出し、高度成長期に入る前で、当時のプロ野球は六大学などの学生野球よりも人気があるとは言えず、後に球界一の人気球団になる読売巨人軍ですら当時は多大な赤字を計上していた。
その後、テレビ時代に入り、巨人軍はメディアグループの強みを生かして放映権料による収益を拡大。長嶋茂雄、王貞治の活躍で9連覇の偉業を遂げるなど人気、実力ともに名門へと駆け上がるうち、潤沢な資金力のある球団になった。セ・リーグの他球団も、巨人を迎えて行うホームゲームの放映権料が貴重な収入の柱となり、黒字または赤字でもわずかな金額に抑えられるようになった。一方、パ・リーグは放映権料によるビジネスモデル構築ができず、一時は関西だけで阪急、近鉄、南海と3球団が競合する状況。どの球団も慢性的な赤字を抱え込み、阪急はオリックス、南海はダイエー(現ソフトバンク)に球団を売却、近鉄は2004年にオリックスとの合併で消滅してしまった。巨人が球界の頂点に君臨する一方で、多くの球団は国税庁が認めた通達に基づき、親会社が宣伝広告費として赤字の損金処理をするため、営業努力が十分でない状況だったのだ。
対照的なのが米大リーグ。実は90年代半ばまでは日本よりも球団数が多かったにも関わらず、市場規模では日本の1,500億円を下回っていた。ところが選手によるストライキでファン離れを起こした反省から経営改革が断行し、ヤンキースやレッドソックスなどの人気球団を中心に収益を拡大。15年経った今では、日本が1,500億円規模のままなのを尻目に、7,000億円に迫る勢いで成長を続けている。金融などの異業種から優秀なビジネスパーソンが続々と参入。徹底したマネタイズやマーケティングで売り上げを伸ばしてきた。
日本のプロ野球も米国の動きに刺激され変化してきている。2005年の楽天参入以後、パ・リーグを中心に地域密着などの経営改革が進んだことで、売り上げを伸ばし、赤字を圧縮するように模索が続いてきた。毎年50億円もの球場使用料を支払っていたソフトバンクに至っては、親会社がとうとう球場を買収。球団の収益改善は進むとみられる。プロ野球の歴史を経営面から振り返ると、税制で保護される産業が「甘えの経営」で停滞するという教訓を知ることができる。