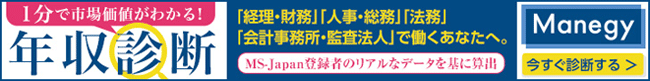経済産業省は、平成27年2月に海外進出する日本企業4286社を対象に課税問題に関するアンケート調査を実施し、5月に「新興国における日本企業の税務対応に係る人材育成・制度整備に関する調査」を公表しました。
調査によれば、移転価格税制・PE認定・ロイヤルティ課税などの二重課税が生じた課税事案が計145件報告されました。145件の二重課税が生じた課税事例のうち、移転価格税制に関するものが46.2%と最も多く、PE認定に関するものが20.7%、ロイヤルティに関するものが16.6%でした。また国別に見ると、中国が39.3%と最も高く、インドが15.9%、インドネシアが13.1%でした。
詳細を掘り下げてみると、新興国においては、グローバルスタンダードから乖離(かいり)した独自の課税根拠により追徴課税を受けるケースが発生していることが分かってきました。今回は、この課税事案への対応事例と今後の課題を取り上げてみたいと思います。
移転価格税制の課税事例
海外の関連企業と取引を行う際に発生する移転価格税制のうち、みなし利益率の適用により、税額が増えたケースが全体の21.4%を占めました。これは、新興国の税務当局が、企業の果たす機能や付随するリスクを考慮せずに企業の利益率のみを重視した結果、追徴課税を行い、また、税務当局による修正の際には、利益率が低い企業や損失が生じている企業を比較対象企業から除外するなどして、利益率を増やす調整をする場合がありました。
このような措置を、OECD(経済協力開発機構)のグローバルスタンダードと比較すると、取引の状況に応じて最適な移転価格算定方法を採用するという、最適法(ベストメソッドルール)の導入により「利益率」に着目した移転価格算定方法の適用が増加したものの、検証対象企業との「機能及びリスクの比較」は引き続き価格算定における最も重要な原則としており、今回の当局の措置は、グローバルスタンダードに則していないといえます。
PE認定の課税事例
次に多かった事例がPE認定です。PE認定の中でも、親会社が現地子会社に対して高頻度で出張者派遣等を行う際、税務当局が当該出張者をPEと認定し、出張者に帰属する所得に対して課税するケースです。具体例として、日本の親会社の社員が現地子会社へ毎月1回(1日)、現地法人へ出張し、年間の出張日数は12日であるにもかかわらず、1日=1カ月とカウントし、計12カ月分の出張者の給与に対して課税するというケースがありました。
OECDのグローバルスタンダードと比較すると、出張者が役務提供しておらず、また待機 状態でもない場合には、その日は日数換算しないとされており、この措置もやはりグローバルスタンダードに則していないといえます。
今後の課題
これらの事案を通して見えてくる課題点は、新興国の課税根拠はグローバルスタンダードから乖離(かいり)した独自のものであること、そしてそれに効果的に対処できる、企業側の税務に精通した人材の不足がうかがえます。
また、訴訟に発展した場合、国によっては納税者勝訴の確率が非常に低いところや、調査官が安易に追徴課税を行うため、裁判で争うこと自体が常態化しているところもあり、今後の新興国における課税事案への対応にあたっては、各国での事案への取り扱いの違いなど、様々な角度による検証が必要である、と報告はまとめています。
【この記事を読んだ方におすすめのサービス】
≪会計業界の転職はプロにおまかせ!≫無料転職サポートサービスとは?
≪転職で譲れないポイントを相談&発見!≫無料転職相談会・無料転職セミナー